小泉進次郎氏の総裁選陣営で“広報班長”を務めていた牧島かれんさん。
そんな彼女が、2025年9月に発覚した「称賛コメントの投稿要請」騒動の中心人物として、大きな注目を集めました。
この出来事は「やらせ」「ネット操作」「ステマ」といった言葉を呼び起こし、
政治とSNSのあり方に一石を投じる問題へと発展しています。
この記事では、話題の「牧島かれん ステマ要請問題」について、
- どんな内容が問題視されたのか?
- なぜ辞任にまで至ったのか?
- 小泉氏や世間はどう反応したのか?
この3点を中心に、分かりやすくお伝えします。
それでは本題に入りましょう。
ステマ要請問題の発覚と内容とは?称賛コメント依頼の実態

2025年9月、自民党総裁選のさなかに持ち上がったステマ要請問題。
この騒動の火種となったのが、牧島かれん氏の事務所が送った「動画への称賛コメント投稿依頼」でした。
問題の発端:メールによる依頼が発覚
報道によると、牧島氏の事務所は、小泉進次郎農水相の総裁選関連動画に対して
「好意的なコメントを投稿するよう依頼するメール」を、複数の陣営関係者に送信していたとされています。
メールの中には、
- 「進次郎さんの人柄や実績を評価するコメントをお願いします」
- 「他候補との差を際立たせる表現も歓迎します」
といった文面があったとのこと。
この行為が「やらせ」や「ステルスマーケティング(ステマ)」に該当するのではないかとして、SNSやメディアで一斉に批判が広がりました。
送ったのは小泉陣営の広報班長を務める牧島かれん元デジタル相の事務所で、コメント例として「ビジネスエセ保守に負けるな」と候補者の中で保守色が強い高市早苗前経済安全保障担当相やその周辺を意識したと受け取られかねない内容も紹介していたという。
引用元:産経新聞
ネット「世論操作」の問題点
問題視されたのは、「特定の候補を不自然に持ち上げるネットコメント」を、
陣営が主導で要請していたという構図です。
特に選挙という公的な場面で、こうした「見せかけの支持」を演出することは、
有権者の判断を歪める恐れがあり、政治倫理に反するとされました。
SNS上では次のような声が目立ちました。
「コメント操作なんて、信用を失うだけ」
「ステマをする政党に任せていいのか?」
「まるで商品PRと同じように候補者を売り出している感じがする」
これにより、牧島氏の政治姿勢だけでなく、政党全体のネット戦略にも疑問が投げかけられることとなったのです。
牧島かれん氏の辞任と釈明、小泉氏の対応も注目に

ステマ要請問題の発覚を受けて、事態は急速に動き出しました。
責任の所在をめぐる議論が起きる中、牧島かれんさんは大きな決断を下すことになります。
広報班長を辞任へ
問題発覚から間もなく、牧島氏は小泉進次郎氏の総裁選陣営における**「総務・広報班長」**の役職を辞任。
その理由については、陣営全体への影響を避けるための「けじめ」とされました。
記者会見などで牧島氏は次のように説明しています。
「私個人の指示ではなく、事務所の判断だったとはいえ、監督責任があると考えています」
責任を認めたうえで、陣営に迷惑をかけたことを謝罪。
一方で、政治活動自体は今後も継続する意向を示しており、一定の幕引きを図る姿勢を見せました。
※引用元:Yahooニュース
小泉進次郎氏の謝罪と釈明
牧島氏の辞任を受けて、小泉進次郎氏も公の場でコメントを発表。
その中で次のように語りました。
「最終的に選対で起きたことは私の責任です」
引用元:Yahooニュース
「国民の信頼を裏切るようなことがあってはならない」
この発言により、小泉氏自身も問題を重く受け止めていることがうかがえます。
同時に、陣営内の情報管理やコンプライアンス体制の見直しにも着手していく姿勢が示されました。
一方で続く批判と不安の声
辞任や謝罪が行われたとはいえ、SNSや世論の反応はすぐには落ち着きませんでした。
- 「責任を取るなら立場だけでなく、説明も徹底すべき」
- 「本人の指示じゃなくても、それを止められなかったのは問題では?」
- 「党全体のネット活用体制を見直す必要がある」
こうした声からもわかるように、今回の騒動は単なる一議員の問題ではなく、政党全体の信頼性にも影響を与えかねないものだったのです。
世間の反応と今後の課題は?ネットと政治の距離感
牧島かれん氏のステマ要請問題は、単なる一議員のミスにとどまらず、政治とインターネットのあり方を根本から問う事態となりました。
ここでは、世間の反応と今後の課題についてまとめていきます。
SNS時代に広がる“透明性”への疑問
問題発覚後、SNSでは以下のような反応が多く見られました。
- 「ネットでの発信が当たり前になった時代、情報の“質”がますます重要」
- 「政党が裏でコメントを誘導していたのなら、それは信頼の損失」
- 「一般ユーザーの声を装った“戦略”が今後も行われるのでは?」
このように、多くの国民が「どこまでが本当の世論なのか分からない」という不信感を抱くようになっています。
政治家のSNS活用に求められるルールとは?
今回の騒動は、「SNSの使い方」に対するルール整備の必要性を浮き彫りにしました。
- 誰が発信しているのかを明示する「透明性」
- コメント操作や“依頼型評価”の禁止ルール
- 陣営やスタッフが投稿する際のガイドライン整備
こうした対策を取らなければ、SNSが有権者との「橋渡し」ではなく、「操作ツール」となってしまう恐れがあります。
牧島かれん氏が果たすべき今後の役割
今回の問題で政治倫理を問われた牧島氏ですが、彼女にはデジタル政策に長けた実力があります。
だからこそ今後は、同じ過ちを繰り返さないよう、以下のような役割が期待されています。
- 自らの経験を活かして「政治とネットの健全な関係」を築く提言を行う
- 若手議員のSNS運用に対する教育・ルール作りへの関与
- 自民党全体のネット発信体制の見直しに関与する可能性
政治の現場で起きた失敗を、次の前進につなげられるかどうか。
それが、今後の牧島かれんさんに求められる大きな使命の一つとなりそうです。
まとめ
牧島かれんさんの「ステマ要請問題」は、政治とSNSの関係に大きな疑問を投げかけました。
- 事務所が称賛コメントを依頼し「世論操作」と批判された
- 批判を受け牧島氏は広報班長を辞任、小泉進次郎氏も謝罪
- 世間からは「透明性やルール整備」が求められている
今回の出来事は、政治家のネット活用に信頼と責任が不可欠であることを改めて示しています。
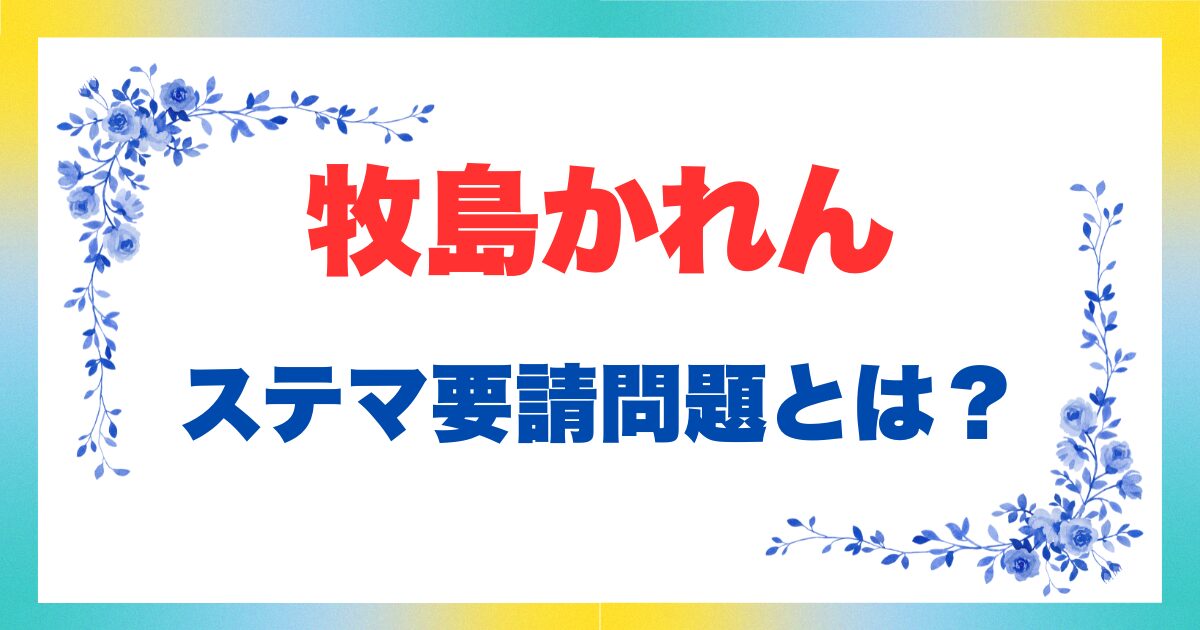
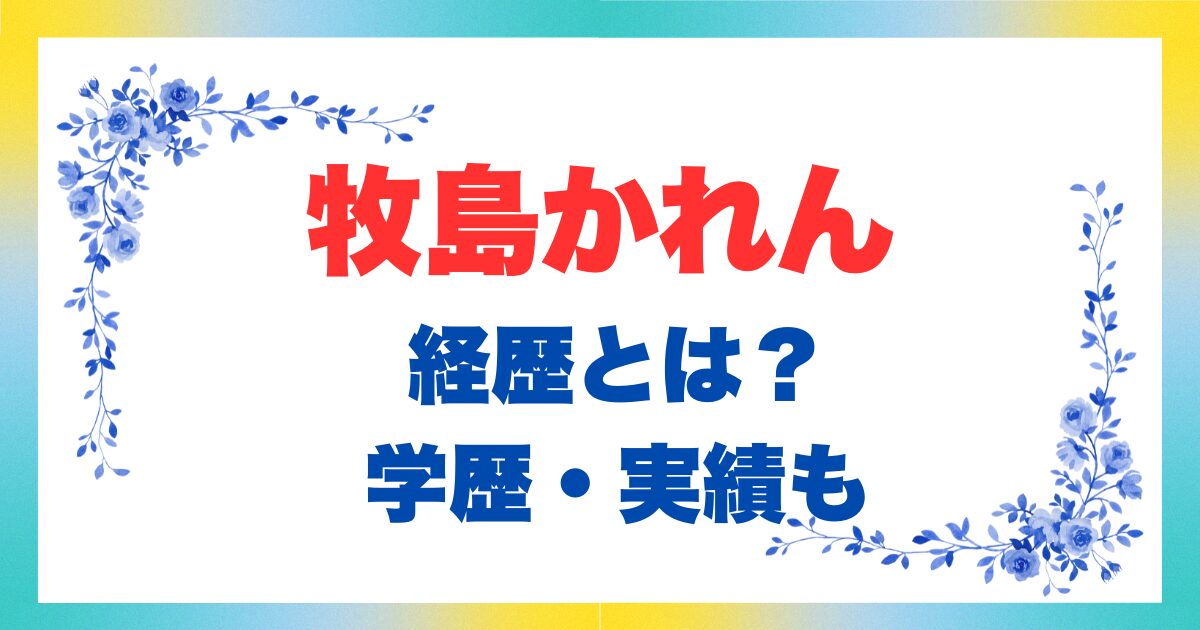



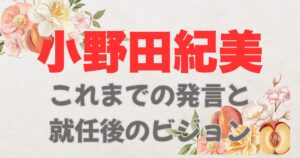
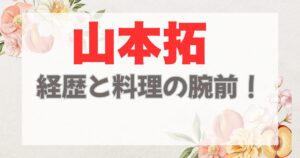

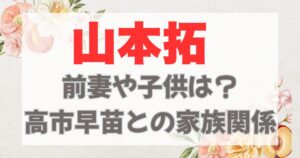
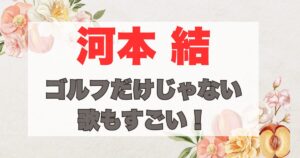
コメント